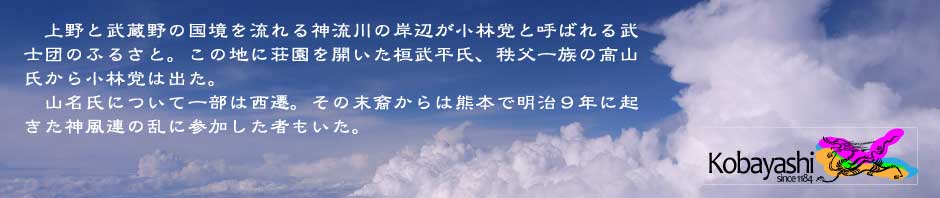「江戸」カテゴリーアーカイブ
【江戸】寛永五年・小林伝三郎江戸への御供を望む
「熊本県史料近世編」第二には、「寛永五年十一月五日覚」という、小林伝三郎が江戸 … 続きを読む
【雑感】江戸時代の心性
明治9年、熊本で起きた神風連の乱に参加した小林恒太郎は、事敗れた後、自宅に戻 … 続きを読む
【雑感】勘右衛門を幸隆に託したのはなぜ?
小林丹波が、子の勘右衛門を愛宕山福寿院にいた細川幸隆に託したのは、戦国の世も終 … 続きを読む
【江戸】細川幸隆、龍王城主となる
細川忠興が関が原の戦いでの功績によって豊前の国を拝領したのに伴い、弟の幸隆も豊 … 続きを読む
カテゴリー: 江戸
【江戸】細川幸隆、龍王城主となる はコメントを受け付けていません
【江戸】勘右衛門、「御前損じ」により知行召し上げ
小林勘右衛門は、細川家が豊前を領していた時代に、当時、隠居していた忠興によって … 続きを読む
カテゴリー: 江戸
【江戸】勘右衛門、「御前損じ」により知行召し上げ はコメントを受け付けていません