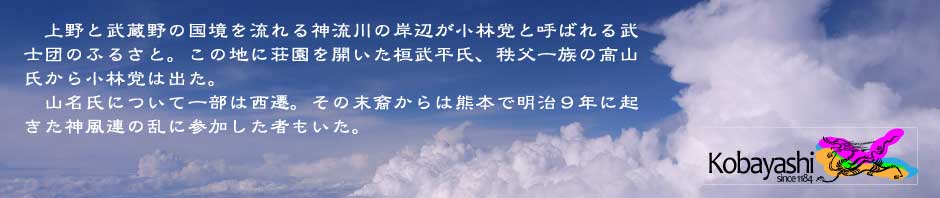明治9年、熊本で起きた神風連の乱に参加した小林恒太郎は、事敗れた後、自宅に戻って切腹。最期のときに、先立つ不孝をわびる恒太郎に、母・ツタ子は安心して死ぬように励ましたと伝えられている。軍国主義の美談に利用されそうな場面だが、後の世の人には理解できない、江戸時代の“心性”と受け止めたほうがしっくりいくような気がする。
小早川秀雄著「血史熊本敬神党」は、こう記してる。
小林は母に向かひ、先立つ不孝の罪を詫び、事此に至りては割腹の外なきを述べしに、母は「ナニ相済まぬ事のあるべき。安心して快く死すべし」と慰め、姉妹にも暇乞ひを為し、それより妻を別室に伴ひ行きて、己の死後離婚再縁の事を頼みたり――。
何も恒太郎の母が、特別に気丈だったわけではないようで、渡辺京二氏の著「神風連伝説」(「神風連とその時代」所収)には、同じような家族たちの姿を数多く紹介している。
米村勝太郎のケース。母は「何のすまぬことがあるものか。お国のためにと思ってやったことじゃないか。おまえの志はよくわかっているから安心して立派に死になさい」と頭をなでさするようにして、いとおしみつつ死なせたようだ――という。
一方で、「息子や弟が死に遅れはしないか」と強迫観念にかられる家族の姿も「神風連伝説」には描かれている。
乱後、自宅に潜伏中の病身の息子を心配して、「なんじの素志はかたくとも、五体はすでに不治の病におかされている。とても再挙の日はまたれまい。ぐずぐずして縄目の恥を受けようより、すみやかに自刃して武士の面目をたてたらどうか。さあ辞世の歌を一つこれにしたためて」――と料紙をさしだした母親。
また、別の家では、なかなか自決しない弟にじれた姉が「それ、またそこへ屋さがしが来ましたぞ。覚悟」と偽って、自決を催促した逸話もある。
そこに後ろめたさや暗さは感じられない。武士の本分の達成を願う純粋な愛情であるとみた渡辺氏は、「男たちに、武士としての最期をかざらせてやればよかった。母は息子が武士としていさぎよい死をとげることを期待し、妻は夫のみごとな最期をさまたげぬつつしみを保った」と解釈している。私もそう思う。
神風連について書かれたものは、当然のことながら、書かれた時代の思想が反映している。
「血史熊本敬神党」が書かれた明治43年は、日露戦争後、庶民にまで国家意識が広まっていったころです。「烈婦」「貞婦」として美化しようという時代の意識も垣間見える。
当然のことながら、彼女たちは難しいことを考えたわけでなく、当時は、だれもが同じことをしたであろう、自然な振る舞いをしただけだったのではなかっただろうか。
それが、現代人はもう知ることも、想像することも難しくなった江戸時代の心性だと思う。