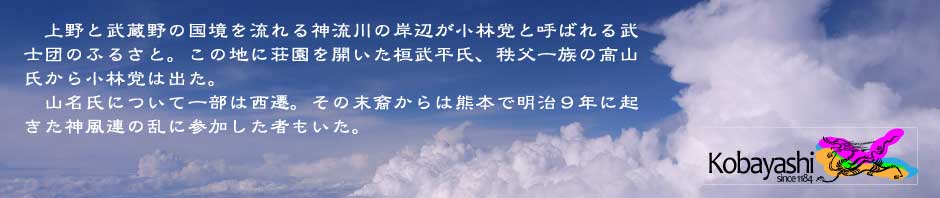小林恒太郎、鬼丸競、野口満雄の3人は、再挙の企てを断念し、恒太郎宅で割腹して果てた。明治9年10月28日のことである。役所に自決を届け出て、検視を終えた小林家では、再び、マシ子の行く末のことが話題にのぼった。
マシ子は、鎮台襲撃の日の朝に夫から挙兵を告げられた。10月24日のことである。
それからは、19歳の妻にとって嵐のような5日間だった。出陣の準備をして夫を送り出し、乱後、官憲の捜索を受けるが、家人とともに知らぬ存ぜぬを通した。夫の不利益にならないように心配りするのは、武家の嫁として役目だったからだろう。
恒太郎は戻ってきて最期の別れができたが、離縁して再縁するように勧められる。マシ子が強く拒み、何とか恒太郎を納得させることができたのだが…。
ところが、恒太郎の遺骸を囲んだ通夜の席で、集まった親族らの間からこの話題が再燃する。結婚わずか6か月での夫の死。しかも、まだ19歳である。子もいない。
この席で口には出すものはいなかっただろうが、乱を起こした熊本敬神党は、いたって評判が悪い。神意を第一とする行動原理は、保守的な細川家中の大多数の武士たちからも“変わり者”扱いを受けていた。
実際、恒太郎の父親の死後、何かと面倒を見てくれた西村仙也という伯父がいる。西村はもともと敬神党の精神的指導者である林桜園の門人だった。恒太郎が敬神党とのつながりを深めていくと、「林先生へは、おれが連れ出しているのではない。恒太郎が熱心に参るのである」と、周りに弁解をしていた、と「神風連血涙史」(石原醜男著)に紹介されている。家中で色眼鏡で見られていたというエピソードの一つである。
親族が集まると、そうした奇矯な者の遺族、さらに加えて、反乱を起こした“賊の遺族”というレッテルを、嫁入り間もない婦人に押し付けるのは不憫だという声が出ても不思議ではない。
だが、ここでもマシ子は強硬に抵抗した。通夜の席を外すと、独り別室で髪を根元から切って、一堂の前にあらわれ、意志表示としたという。
通夜の席も水を打ったように静まり返った。「血史熊本敬神党」(小早川秀雄著)ではこの時の様子を、「母をはじめ、座にありし人々、いずれも涙に面をおおわぬはなかりき」と記している。
恒太郎の家族はその後、賊の遺族としてに細々と暮らしていたようだ。家は妹のアサ子が婿を取ることによって継いだ。幸い、西南の役による混乱も何とか乗り越えて熊本の地を離れることなく、落ち着いた生活を送っていたようだ。そこには家族の一員としてのマシ子の姿もあった。
だが、このままでは終わらなかった。新政府に仕える、マシ子の兄・鎌田景弼が熊本から家族を挙げて東京に移り住むことになった時、マシ子の離縁問題がまた持ち上がった。3度目になる今回は、マシ子には知らせずに事が進められた。
一時的な里帰りのつもりで、マシ子は兄のいる東京に向かった。ところが、東京滞在中に離縁の申し込みが小林家になされ、受け入れられた。
これから以降は少々長いが、「血史熊本敬神党」の文章を引用する。
その後、マシ子は、鎌田氏の佐賀県令たりし時、ある人に再嫁し、二、三人の子供までも出来たるが、その夫の素行乱れしかば、マシ子はやむなく里方に帰り来たり。
一日小林家の川尻町にあるを訪ひて、深く自己の過ちを謝し、「わらわがあまりに不甲斐なかりしため、貞節をまっとうするあたわずして、再嫁することとなり。今日不幸の身となれるは、畢竟、神罰なり」と。
涙を流して懺悔し、数日間滞留して帰りしが、かくて神経を痛め、自ら刃に伏して死したり、といふ。
また、「神風連血涙史」では、小林家に逗留し、ツタ子もアサ子もマシ子の苦労を慰め、この時はマシ子もうれし涙を流したという。その後も時々訪ねて来て、手紙のやり取りも続いた。
だが、その最期は、「女心の終に思いあまってか、不眠症を発し、憂愁に日をおくる中、一夜、人知れず自ら刃に伏したといふ」と書かれている。
時代に翻弄された、と言うのはたやすい。だが、何よりも悲しいのは、マシ子自身が「自分が悪い」とだれよりも思い込んでいたことのような気がする。