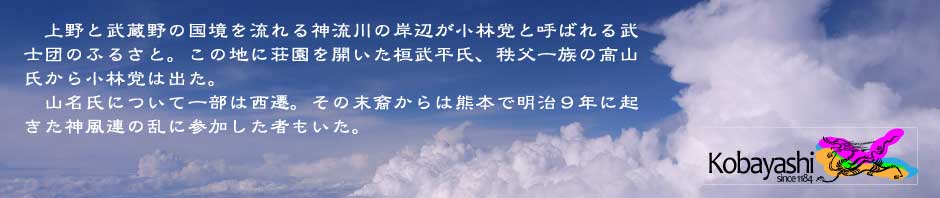去程に十二月二十九日くれほどに、奥州、小林をよびて、宣(のたまひ)けるに、「われこの間、当社をあがめ申(もうし)、賀茂社を造営したてまつる事はただ、大方の敬信のみにあらず。この一大事を思立(おもひたち)祈祷の一をかねたる也。
また、つらつら、事の心を案ずるに、新田左中将義貞は、先朝の勅命を承て上将の職に居し、天下の政務に携(たずさわり)き。我その氏族として国務をのぞむ條、謂(いわれ)なきにあらず。されば、先年事の次(ついで)ありし間、南朝より錦の御旗を申賜て今にありけり。今度、この旗を差(さし)て合戦をすべし。もし、軍(いくさ)に利あらば、争ふべき人なければ、御分、執事職に居して、毎事を申沙汰候へ」と委細に補せられければ、
義繁、更に返事をば申さずして、ただ、涙にむせびければ、奥州、案に相違して、あきれ給へるところに、小林、ややありて、申しけるは、「この間も、内々、申入度存候つれ共、播磨殿御越候て、事すでに御治定候ぬ。その上、近年は宇屋・蓮池やうの物に毎事を仰付(おうせつけ)られ、今般の御大事をも人しれず仰合(おうせあわせ)らるるうえは、不肖の身を以て愚意を申(もうす)に及ず。ただ、愁涙を含てまかりすぎ候き。そもそも当家の御事は、先年御敵にならせ給て候し時も、御後悔ありて、故殿御参の後、御一家の間に十余ヶ国の守護職を御拝領のみならず、諸国の御領どもその数をしらず。それらはただ、上意の忝(かたじけなき)至(いたり)也。されば、世こぞって賞翫申事、日比に超過せり。これに依て、御被官の輩ややもすれば在々所々にて強々の沙汰共仕て、一家の御悪名を立申(たてもうす)事、骨髄に入て口惜(くちおしく)存候。さるに、何にもして道をあらため、御家門一同にさ様の非義を誡(いましめ)られて上意をも重し申され候へかしとこそ、明暮歎存候ところに、結句、今御謀反の御企におよび候間、仰蒙候趣一事としてうつつとも存候はず。さればいかに神に忠をいたさせ給ふとも、全く正八幡大菩薩も賀茂上下の神慮にも、神は非礼を受けずと申候へば、御加護あるべしとも存候はず。また近年、莫大の御恩をわすれて、上様へむけ申て弓をひかせ給はん事、世の人定(さだめて)不思議のおもひをなすべし。または、天の照覧もはかりがたし。たとえ、またいったん、御合戦に利ありと申とも、天下の大名、誰人か今更、御所様をすてまいらせて、当家奉公のおもひをなし候べき。然(しから)ば、神明仏陀の御加護もなく、諸人上下かたむけ申さば、何の助あてか始終御代をめされ候べき。これを歎て首陽に入らむとすれば、弓矢の道、既にかけて子孫ながく奉公の儀をたつ。これを進て忠功を致さむとすれば朝敵の責をのづから至て、一身をおくに所あるべからず。ただ今度合戦あらば、義繁に於ては一番に討死を仕て泉下に忠義をあらはすべきにて候。さらんとりては執事職の事は他人に仰付らるべし」とて、目ももちあげず。涙をおさえてまかり立ちければ、さばかり勇(いさみ)進み給へる奥州をはじめとして、諸人耳を澄ましつつ、且は歎(なげき)、且は感じ、皆鎧の袖をぞ濡らしける。
その後、上総介高義を近付(ちかづけ)て、「ただ今の小林が気色定て楚忽の死をいそぐべし。これまでまた治定したる事を思とどまるべきにもあらず。所詮、明日は小林と御分一所に成て毎事を談合候へ」と宣(のたまひ)ければ、上総介も心の中には残りとどまりて、傾く運の末を見きかん事はあるまじき物をと思われけれども、「畏て承候」とてやがて退出し給けり。されば晦日朝、二条大宮の一番の軍に上総介も小林も一度に討死しけるこそ、哀なりし事どもなれ。
(岩波文庫「明徳記」36頁)