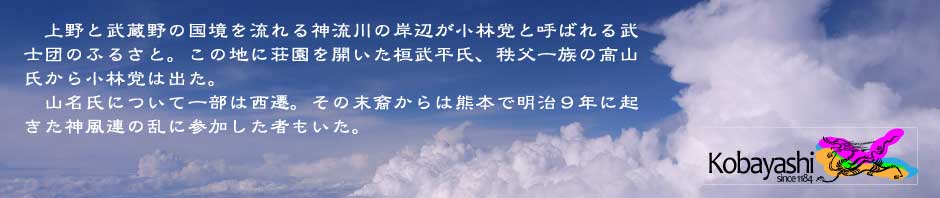去程に、軍は十二月二十七日を定(さだめ)たりけれども、紀伊国の勢そろはざりけるに依て、匠作おそく着給(つきたまひ)ければ、八幡にも今度の合戦せんとなり勢そろはでは如何とて、合戦は延引してげり。
さらば軍は正月二日と定(さだめ)たりし処、峯の堂八幡の軍勢共夜ごとに減ずるよし申しければ、「かくてはいかがあるべき。さらば年内も明春もいづれか合戦あるべき」とて、召具(めしぐせ)られたりける陰陽の博士にうらなわせられけるに、博士占形をひらきて、しづかに合戦の吉凶を勘(かんがふ)るに、「奥州は水性の人也。ときは今冬也されば水王して年内合戦あらば治定の御勝」とぞ勘申(かんがえもうし)たりける。奥州誠に快げにて、「さらば方々の責口へ相触(ふれ)て三十日、時定の合戦」とぞ定られける。
この陰陽博士、小林上野守を閑所に招て内々ささやきけるは、「御合戦吉凶の事仰下され候つる間、勘文の趣をば大概申上げ候き。夫占と云は推條をもて本とし、了簡をもて宗と仕(つかえつる)事にて候。奥州水性にて御渡候間、冬は王して御合戦利有べき事は治定と申ながら、十二月は冬の囚の位にて気春に近し。又水は北より南へながるるは陰の道にて逆なり。されば御本意を達せられん事如何と覚候。哀(あわれ)此辺に御陣を召れて打手の下向を御待候へかしとこそ存候へ。この分を申度候つれども、是まで思食立(おぼしめしたち)候事にて候へば、御気を損ぜられ候て、『何の勘文にみえたるぞ。又わたくしのすいか。然らば勘文にて利有とみえて、私に負(まく)べきよし推量はめづらしき勘進かな』と、仰を蒙候ては、生涯と存候間、勘文のおもむきばかりを申て候はいかに」と申ければ、義繁申けるは、「元より此悪事を思立て軍に勝て身を立(たて)ん料とは更におもひより候はず。ただ一家亡(ほろび)て身を失(うしなわ)ん為と存ずる計(ばかり)にて候。ただ人のほろびんとてはわれ悪事をおもひたつ事昔より定れる事にて候間、うあらも文も不審なる事にこそ入候へ」と事のほかげに申ければ、人々皆この儀に同じにて、更にいさめる気色なし。
(岩波文庫「明徳記」34頁、以下、「小林義繁氏清に諫言す」に続く)