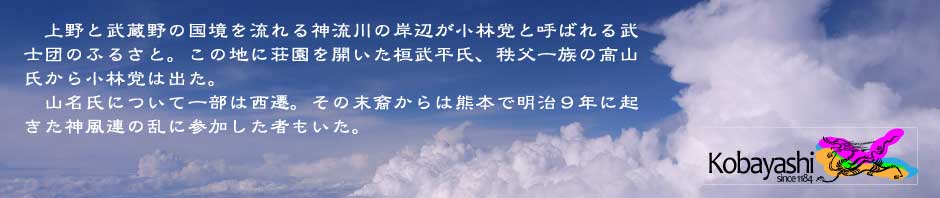さるほどに十二月晦日の卯刻に、四條大宮よりのぼり押し寄せて、「山名上総介高義・小林上野守義繁、今日の軍(いくさ)の先がけにて、討死する」と声々に呼ばわりて、時を同どぞあげたりける。大内左京権大夫義弘是を聞きて、「一番勢、宗徒の者ども、皆この攻め口へ寄せたりけり。是はのがれぬ所なり。敵は定めて大勢にてぞあらむ。この陣小勢なりといへども、面々は皆、名を知られたる人々なり。西国にては度々の合戦に毎度、名を揚げたる兵なれども、都あたりの軍(いくさ)はただいま是を始めなり。われらが安否、この軍(いくさ)にあり。一人も残らず切死(きりじに)して名を萬代の誉れに残し、尸(かばね)を一戦のちまたに捨てよ」と呼ばわりて、かねて定めたることなれば、五百余騎の兵ども、一度にはらりと降り立ちて、楯を一面につき並べ、射手の兵二百余人左右の手さきに進ませて、「中を破られるな。敵、もし馬にて破りて通らんとせば、馬を切りてはねさせよ。落ちらば押さえて差し殺せ。もしまた敵も降り立ちて、切りてかからば閑(しずま)りて、手もとへ近づけ、組討にせよ。敵引くとも追うべからず。手いたく切りてかかるとも、一足も退くな」と大音を揚げて下知しつつ、わが身も真前に降り立てり。
権大夫のその日の装束(いでたち)には練貫を紺地で染めて縅(おどし)たる鎧(よろい)に、同毛の五枚甲の緒をしめて、二尺八寸の太刀をはき、三尺あまりなりける長刀を引きそばめ、軍勢と同じく降りたれども、青地の錦の大母衣(おおほろ)をかけたりければ、枯野(かれの)の霜に花そひてまぎるる方もなかりけり。
小林が先懸(さきがけ)の兵二百余騎、二條大宮へ駆け出て、敵の陣を見渡せば、雨は宵より降りはれて、暁ふかく霧こめて、物色はさだかに見えねども、東嶺にわかるる横雲の、ひまよりしらむ夜は明けて、篠目見ゆる程なるに、ひた甲五六百が程をり立て、南向きに楯を一面につき並べ、其のひまひまには兵ども、枯野になびく尾花のごとく、切っ先をそろえてしづまり返りてひかえたり。内野の方を見渡せば、陣々の大勢打立て、大旗小旗ゆらめきわたり、五六萬騎もあらんと、雲霞のごとくひかえたれば、大山に向かう心地して、上総介も小林も退屈してぞ覚えける。
さるほどに二條大宮より軍(いくさ)始まりて、馬の足音、ときの声、天地もひびきわたりたり。権大夫の兵は神祇官の森を後ろにあて、射手の兵物(つわもの)は、皆、胴丸、腹当、帽子、甲にて、楯より左右に流れいでて、矢さきをそろえてさしつめ引きつめ、雨の降るごとくにぞ射たりける。小林が兵、射立てられ、馬の足を立てかねて、是もはらりと降り立ちて、大内勢の真中へ、鋒(ほこ)をそろえてきている。敵味方入り乱れて、分々の敵に相合て、大宮を南北へ、二條を東西へ、追いつ返しつ、まくつまくられつ、五人十人、手に手に手を取り組みて、一度に討死するもあり。ことはりなれや、西国に名を得たる大内勢と、中国にては勇士の聞こえある山名方の「鬼ここめ」なれば、互いに勇み進みて、ただ死を限りに戦うものはあるけれども、命を惜しみて一足も退くものはなかりけり。敵味方のわきもみえず、二三百人死にかさなりて、血は路径の草を染め、尸(かばね)は原上の墓をなす。慙(はじ)なしといえども愚かなり。
かかりけるところに、上総介高義、小林に向かいて宣(のたま)いけるに、「この軍(いくさ)は味方の利あるべしとは覚えず。とてものがるまじき軍(いくさ)なり。さらんとりては、一騎になりとも、御前近く駆け入りて、御陣の味方を枕にして死ぬよりほかのことはなし。敵はみな馬放れたれば、なにほどのことかあるべきなれば、大宮をのぼりに駆け破りて、御所近くまいり寄せて、討死をせばや」とのたまいければ、小林、もっともと同じつつ、死に残りたる兵ども三十騎ばかり、ときを同とあげて駆け通る。権大夫是を見て、「一騎なりとも敵を上に通したらんはただ、この陣の不覚なるべし。義弘討死せざらん程は一人も通すまじきものを」と言い、神祇官の東おもて、冷泉大宮へ、横合いにむずと走り出でて、駆け通らんとする馬の●尽(むながいづくし)、二重皮、四肢、平頸、鐙(あぶみ)の鼻切りては切りすえ、薙(な)いでは薙ぎふせ、落ちる武者をば首をとり、戦物をば小具足も鐙(あぶみ)もたまらず同切て、権大夫の長刀の刃にまわる人馬ともに多くはここに討たれけり。
(岩波文庫「明徳記」46頁)