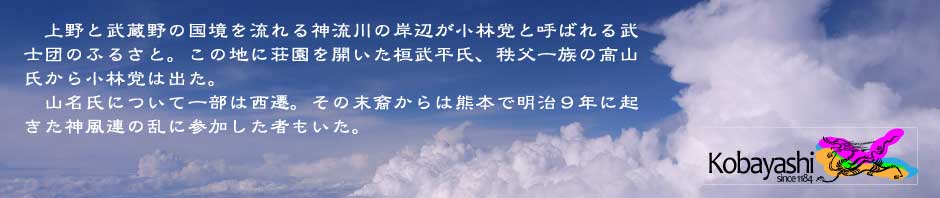明徳の乱を描いた文学に、軍記物語の「明徳記」と、古作の能「小林」(謡曲)がある。そこでは、乱の大将である山名氏清に仕える山名家の重臣で、大義名分のない反乱を諫め、潔く討ち死にする小林上野守(上野介)が、理想的な古武士の姿として描かれている。だが、能「小林」や明徳記の世界を史実と比べてみると、矛盾を感じざるを得ない点もある。
そもそも山名家は、幕府に従順でないところに、その特長がある。11か国の領有も、幕府から与えられたものではなく、自らの力で切り取ったものだ。幕府に対しては、力による駆け引きで対等に渡り合ってきた家柄である。
小林一族にしても、山名時氏のころ以来、山名家の執事として先頭に立って幕府への反抗を指揮してきた。それが一転、明徳の乱では、君臣の順逆を持ち出し、主君を諫止する姿は不自然である。
山陰での自立時代とは代替わりしていることを考慮しても、それほど観念論的になりえるだろうか。ずいぶん前に下賜されていた南朝方の旗を持ち出して立てようとした氏清の方がわかりやすい。
明徳記とそれを題材にしてつくらた能「小林」に登場する小林上野守の行動は、幕府側に都合よく脚色されたという推測も成り立つだろう。
では、氏清に対する諫止はなかったのだろうか。仮にあったとすれば、山名家の分裂を諫めたのではないか、と想像される。山名家の惣領は、師義‐時義‐時煕と伝えられていくうちに乱れ、そこを義満に利用され、今回の乱につながっていく。
氏清は、もともと義満と結び、惣領を“横領”した側である。だが、それからまだ日が浅くて惣領権が確立できていない状態で挙兵を余儀なくされている。それが無謀であり、心ある臣下であれば、主君に意見しなければいけない場面だ。
実際に戦闘が始まると、丹波から動員された久下、中沢といった国侍らは、戦いもせずにいち早く幕府軍に投降。時氏時代に関東からつき従ってきた小林、土屋らは奮戦の末に壊滅している。土屋党にいたっては一時に53人が討ち死にしている。
「大義名分のない戦とわかっていながら、主君に殉じ、死に急いだ」と文学的修辞により美化されているが、ここにも体制側の作為が嗅ぎ取れる。
実際、明徳の乱以後、小林や土屋の一族は山名家の表舞台から姿を消しているので、大打撃を蒙ったことは事実と見ていい。
南北朝のころより戦闘には滅法強い山名軍という評判に加え、両国から幕府軍に拮抗する軍勢を催して対陣したが、戦闘は1日であっけなく終わっている。
戦意の乏しい多くの兵の中にあって、譜代の家臣のみが孤軍奮闘して玉砕したといったところが実態ではなかったか。
惣領権が動揺している最中に、在地支配も中途半端なまま、最強山名軍団の幻想のもと挙兵してしまった、と推察することも可能だ。
山名軍団の虚名におびえた幕府方守護大名たちの和平論を一蹴した義満が、一番、冷徹に現状を分析したマキャベリストだったのだろう。