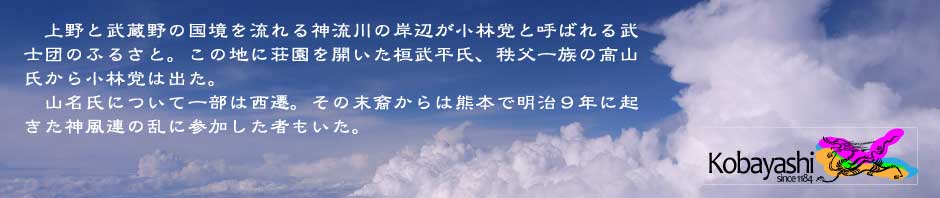明徳の乱(1391年)は、山名陸奥前司氏清が修理大夫義理の軍勢を合わせて南から京を狙う一方、播磨守満幸は西から攻め入り、旧平安京の大内裏跡に広がる内野で、足利義満の幕府軍と雌雄を決するという軍略を描いていた。今回は、戦端が開かれるまでの山名軍の動きに焦点を合わせてみる。
乱直前、山名一族が守護を務めていた国を列挙する。
氏清が丹波、和泉、山城、満幸が出雲、丹後、義理が紀伊、美作、氏家が因幡――という具合に、乱に加担する者で計8か国を領していた。
山名方の挙兵が避けられないものとなってきた様子を、「明徳記」はこう記している。
氏清が兄の義理を説き伏せ、一族の参加が決まると、12月23日には、山名中務大輔氏家が白昼、京を出奔して、八幡(石清水八幡)に入った。これが知れ渡ると、京中の人たちが家財道具を運び出す避難騒ぎが起きている。
大乱になることは、だれもが容易に想像できた。
次いで丹後から満幸が数千の軍兵を率いて丹波にのぼってきた。和泉の氏清は「雲霞の勢」を集めて、八幡に陣を布く。義理は、紀伊、美作の兵を合わせて、天王寺に集結し京で戦端が開かれたら、渡辺を越えて摂津から山崎を通って攻め込むことになっていた。
こうした不穏な情勢は各地の武家より、幕府に届けられている。
丹後からは結城十郎満藤が12月19日に、早馬で、満幸が丹後国内の寺社本所領の幕府方の代官を追い出し、17日には丹後やその他の国の兵が集まり、合戦の用意を進めている、と報告を上げた。
河内の守護代遊佐河内守国長は、隣国の和泉の様子が注進している。「氏清が戦の用意を進めており、近日中に出陣する様子である。河内国を通る場合は、合戦して進軍を阻む」と伝えている。
24日には、義満が義理にあてて書を送って問いただしているが、義理は「氏清・満幸等が近日の振る舞い、是非なき次第にて候」と答え、事ここに至っては、もはや致し方ないとの考えを述べている。
氏家も京からの出奔に際し、「この上は力なし」と言い残している。因幡国の守護代入沢河内守行氏がすでに前日、行動を起こしていることから、傘下の武将に背中を押されたような形での挙兵だったようだ。
いよいよ戦機が熟してきた。