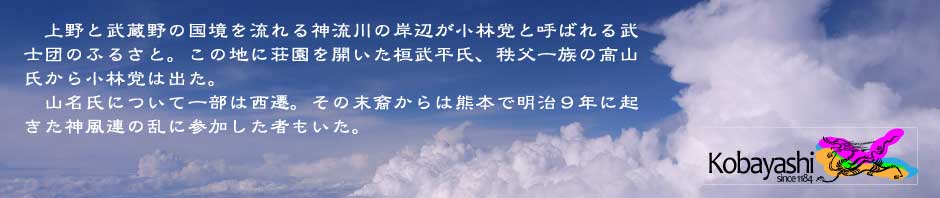倉吉城主山名小三郎氏豊正統の事 附り山名満幸因州落の事
夫れ花に開落あり、月に盈虧あり、盛なるもの必ず衰へ、歓楽極て哀情多きは人生の常也。ここに伯州倉吉の屋形山名小三郎氏豊は山名氏の正統にして、其祖山名伊豆守時氏因伯両州の太守として在国あり。嫡子師義家督相続ありて武威は赫々として旭に輝き、後に出雲隠岐美作等を切り従へ、五ヶ国の領主となり、二男修理太夫義理は紀伊国を領し、三男陸奥守氏冬は因幡の守護となり、四男中務太夫氏清は丹波の領主となり、五男伊予守時義は但州の守護、六男左馬亮氏里、七男上総介義始、八男主殿介とて何れも官禄他に越て肩を並ぶる人もなし。嫡子師義死去の後は、長子義幸相続あり。されども其身病気にて舎弟満幸上方に参勤す。其後但馬の守護山名伊予守時義の息宮内少輔時煕、舎弟右馬頭氏之逆意を企て、将軍に背きたるに依て、満幸を討手となして差遣はされしが、満幸戦ひ勝利を得て功によりて但州を加増拝領したりしに、時煕等間行して京に上り、暫く清水寺に潜居して屢々書を将軍義満に献じて罪を謝し、和を乞ひし程に、後許されて其の旧封に復し、是により満幸大に怒り将軍我を欺くとて、遂に幕府に叛きて兵を挙ぐ。幕府よりは此時討手として山名右馬頭を差向らる。満幸忽ち敗北して倉吉に籠城せんとしたれども叶はずして、因州浅津の辺にて隠世して行方知れずなりけるが、其後遂に探し出されて誅戮にあひ、是より伯州は山名右馬頭氏幸の所領として、子孫末永く倉吉城に居る。小三郎氏豊は此の末葉なり。
(羽衣石南條記巻下 十七—十八頁 大正四年十月発行「因伯叢書」)
南條小鴨山名橋津合戦の事 附り南條元秋討死の事
ここに倉吉打吹の城主山名小三郎氏豊は、元但州の守護山名時義の二男氏之の末葉にして、右馬頭より八代の子孫なり。南條氏羽衣石籠城の節は、南條に加勢して之も同じく籠城して居られけるが、此時吉川勢元長の下知を請けて所々を徘徊し、在々に放火し、又は民間の米穀を奪ひて持ち去る等、狼藉限りなきによりて、小鴨倉吉羽衣石三城主とも大に之を憤りて、諜し合せて一気に駒山へ押寄せて勝負を一戦に決し、日頃の鬱憤を散せんと、各同意し日限既に定まりけり。此事早くも駒山に聞へければ、駿河守は諸将を招き寄せ、敵已に我が思ふ図にあたれり、近日此表に押寄せんと議する由、是れ味方の幸なり。併し敵は小勢なれども皆血気盛の将士なり。殊に永らくの籠城にて気を屈したる強兵ども、身命を顧みず無二無三に突掛るべし。吉川吉岡の両将は二千余騎を卒して出で、敵兵日下の川を渡らば味方も湊川を渡りて備へを立つべし。敵いらつて攻懸りなば、中を割って両方に別れ、備を乱すことなかれ。又左馬亮は茶臼山の勢を卒して浜手の松蔭に伏せ、敵の先陣川岸近くに進むを待ち、相図の鐘を城内より撞くべし。其時三手の勢一度に押懸って、敵の後を遮り、敵を真中に取込て攻入るべし。城中よりも突出てて頻りに太鼓を打つ時は、敵敗軍の色ありと悟り、息も継がず相戦ひ、一騎も残さず討取るべしと巨細遺さず軍令を示して、寄来る敵を待受けたり。かくて天正八年八月十二日、南條伯耆守元続、山名小三郎氏豊、小鴨左衛門元清、南條兵庫頭元周、同九郎右衛門元秋、各日下の端へ出張して合戦の評定あり。先陣は山名勢八百余騎、右陣左陣と相定め、二陣は小鴨八百余騎、三番南條元続一千余騎、後殿は南條元周三百余騎、各評議一決して、合戦は明日辰の刻とぞ定めける。さて其夜は日下の屯所へ宿陣し、明くれば八月十三日、先陣山名小三郎氏豊錦の直垂に緋縅の鎧を着し、弓脇挟み、矢筈たかに負なして、駿馬に打乗り白旗真先にかざし、勇み進で出ければ、流石に伊豆守時氏の末葉天晴器量ある大将よと誉めぬ者こそなかれけれ。其外小鴨南條の人々も、我劣らじと物具鮮かに出立ちて、日下の川を打渡り、魚鱗に備へて敵陣間近く押寄せたり。さて敵方は吉川式部、吉岡越後、二千余騎を二手に分け、橋を渡して備を立て、両軍鬨の声をあげ、仕寄せの大筒種ヶ島、轟々殷々として鳴り渡り、天地に響きて夥し。時に持楯畳楯亀甲を築立々々、暫しは矢軍にて挑み合、騎馬武者歩行武者鑓の穂先をならへ立、両軍颯つと入みたれ、追ひつかへしつ暫しが間戦ひしが、両軍たがひに引分れ、しばらく息を継ぎにけり。時に南條元続は家臣進ノ下総を招きて、今日の合戦の様をかんがへ見るに、味方の軍勢南にあり動ひて雷の走るが如く、敵の軍勢北にあり静にして波の寄するが如し。動静水火相戦ふ時は、多くは味方に過ちあり。殊更敵兵の静まり返りて些とも干戈を動かさず。是弱を示し寄手を誘ひ寄せて深入させ討取らんとの計略ならん。又一つの不審あり今朝海上より白鷺下村浜手の松原の上を翩翻として翔りしが、俄か驚きし有様にて列を乱して飛び去りぬ。是雁行列を乱すと同様、必定浜の手へ伏兵ありと覚へたり。此旨を小鴨山名の両将へも知らせよと有りければ、下総畏つて早速此旨を相達しぬ。小鴨は信服しけれども、山名は血気一方のみの勇将なりければ、是を聞て申す様、是等の儀何程の事か有らん。今斯く勝色に臨んで僅かの事に臆病を構へ、をめをめと引くべけんや。縦ひ謀計にあたりて敗軍に及ぶとも悔いず。日比の鬱憤いつの時にか晴らさんやとて、何の猶予もなく駆けよ者共押寄せよやと、頻りに下知をなしけるに、是により先陣の山名勢は鎗の穂先きを並べ立て、錣をかたふけ喚き叫んで突懸かる。敵兵は山名勢の進むを見て、兼て相図の事なれど、合戦をばわざと手弱くもてなして、双方へ颯と引別れて退け去れば、山名勢勝に乗じて真中を突割つて、川岸近く攻寄せける。南條小鴨の人々も是を見て心ならずもあとより続いて押出す所に、駿河守は城中より此形勢を見て時分は今ぞと采配を振り上げければ、相図の鐘を撞き鳴らすや否や、浜の手の伏兵一度に起って三方より打寄せ、寄手を取囲むにぞ、是を見て城中より城戸押開らき用意の舟橋引渡して、真しつくらに突き出て、四方より押包て火水になれとぞ攻戦ふ。馬煙空を蔽ふて八方暗みわたり、馳違ふ轡の音打合ふ刃の光、実に修羅天帝の戦も是には過ぎじと思はれて凄まじき言はん方なし。寄手は是に揉み立られて、備立て四度路に成りければ、元春は之を見て頻りに押太鼓を打たせて、揉立て揉立て下知あれば、南條小鴨の両勢は少し趾にありける故、沢沼川を一面浅津浦を押渡り、長江表へ一連に成て敗走す。敵兵続いて追ひかけければ、兵とも取て返して川岸を小楯になして火花を散らして戦ひける。此間に南條豊後入道宗勝の末子九郎左衛門尉元秋は、若武者の事なれば、敵に後ろを見せん事口惜とや思はれけん。一隈岸を小楯に取って、引兼て居らけるを、敵兵大将と見るよりも弓鉄炮を四方八方より放ちかけ、雨霰の如く打ち懸けければ、矢面に立つたる兵三人一度に打倒さる。又元秋も鎧に立つ矢は蓑毛の如く、既に危ふき所なりしが、津村長門遥かに此形勢を見て、今日の殿軍なりしが、鎧の縅色馬の毛色元秋公に紛れなしと、四五十騎にて取て返へし直に馳付、元秋の矢面に立塞がりて、命も惜しまず防ぎ戦ひ、敵も少し退きければ、長門は元秋に向ひ申けるは、味方の大将方未だ遠くは落ちさせ玉はじ。追付かせ玉ふべし。長門はここに止まり防矢仕候也と申けれど、元秋答へて斯く迄数ヶ所の深手を負ひきたなくも何迄行くべきぞ。只此所にて潔よく討死せんと有けるを長門は元秋の馬の頭を押戻して仲間をはたとにらみて、ハヤハヤ馬を追立てよと、元秋を退かせ参らせて、長門も今は心安しと寄来る敵に渡り合ひ、臨機応変時にあたりし津村が勇猛、向ふ敵を真甲胸板左右の腕遁行くものの押付くさ摺のはづれ、或は胴中車切縦横無尽に切伏せ切立て追捲くれば、敵兵之に肝を消し敢て近付者もなく、遠矢に射てそ居たりける。長門は最早よき折ぞ兵ともに目くばせし、駒の首を引返して殿軍をいなしたりけり。敵も見懼やしたりけん追来るものもあらされば、静々として引きにける。扨も痛しきは元秋也。長門に別れて後門田の前を打過ぎて植木縄手に懸りければ、手疵次第に痛みを増し馬よりどうと落つ。鬼助驚きやがて扶け起し参らせ、馬に乗らすれば、復も落ち給ふ。かかる事二三度にて今は息も絶へ絶へなり。是によりて傍への辻堂に入れ兎角案じ煩ひぬ。此時鬼助思ふ様所詮此の様にては君の生命は助かるまじ。左らば元秋の首を取て敵兵に降らば、我が命ばかりは助かりなんと、俄かに悪心を起し、遂に主人の首を打落して、馳来る敵に腰をかがめ、南條元秋の首を打取て差出せしに、敵にあらずして津村長門なりしかば、南無三宝と云ふ声に鬼助も心付き、俄に逃んとするを津村頓て引握んで、大地にどうと打ち居へて、此の八逆の大罪人思ひ知れと、首搔き取りぬ。噫口惜しかかる事ありと知るならば長門御供すべかりしにと、後悔するも詮なければ、泣く泣く死骸を下部に取もたせ、羽衣石を指して帰りけり。然るにその妄執散じやらず、彼の辻堂へ留まりしかば、屢々通行人も悩ますことありし故に、後に小社を建てて若宮の荒神とて、霊験を見はししとなり。
(羽衣石南條記巻下 十八ー二十三頁 大正四年十月発行「因幡叢書」)
山名小三郎氏豊湊川合戦の事
去程に山名小三郎氏豊は、敵に四方を囲まれて、其勢僅か二百騎計りに討なされ、湊川を後にして隙を伺ひ切腹せんと、八方へ眼を配って居られける。比しも八月霖雨の後、小鴨竹田の水かさまして、湖水は浸々として水を湛へ、湊川へ引流れ渦巻しつつ漲りて、左右なく渡るべきやうもなく、暫しためらふ所に、敵兵次第に迫りて来りて攻戦へど、味方は皆々戦ひつかれ、其上討死手負のもの多く、川岸に攻め寄せられて、東の洲崎へ取上るを、駒山勢之を見て、それ余ますなと東の岸より、一斉に駆出て、山名勢を真中に取捲きて、息も継がせず攻立る。山名勢少しと雖も、皆々譜代恩顧の忠臣義士、福間山下多田石原太田竹田佐野河村首藤竹串穂田福塚等の諸士、大将を真中に打圍ひ、多勢の中に割って入り、北を切抜け南へ廻り、縦横に馳せ戦へば、さしもの敵の大勢も、是にしらみて群ら群らとして退く所を、東の一方を切り抜けて、其勢纔に百騎計り。一同馬に鞭を加へ、一さんに東を指して落行きけり。敵兵猶も喰留めんと、我先にと追いかけたり。宇野坂の細道にて是屈強の要害なりとて、平井主水福塚猪之助首藤弥左衛門取て返へせば、三刀屋久兵衛宍戸半左衛門、一度に太刀を抜きつれて打合切合しのぎをけづり、火花を散らして戦ひけるが、味方の平井は敵の三刀屋に討れ、敵の前沢は味方の福塚に斬られ、首藤と宍戸は相討にして両方へ倒れける。敵も味方も義を泰山より重んじ、命を鴻毛より軽んずる人々なれば、屍は原野に積まれ、血は草莽を染むるを覚悟して、双方一歩も退かず。時に大将氏豊は、家士小林源蔵と主従二騎にて落行たりしが、中途にて馬を路傍に放ちて、宇野坂より右に付て宮内山へと入り込み、暫らく息を休めらる。此時福間太郎は馬の太腹を射られて、歩行して落行きけるが、大将の乗捨られし馬を見て、扨ては此の山路に入らせ給ふかろ、先つ主君の安体を悦び、馬の蹄の跡を敵方に知らせじと、頓て其馬に打乗て、浜路を東へ向けて駈行きけり。かくて山名氏豊主従は宮内山に分入って、渓水にて喉を潤ほし、社の方へ打向ひて、一心に祈誓をこめ、我行末を加護あらせられ給へと伏し拝みて、是より羽衣石の城に入らんかと思へども、東の方は吉川彦七郎が白石の砦、往来を塞ぎて居れば、鳥も通はぬ要害也。浜辺は追手の兵士の東西に走り廻り、後ろは駒山の城にて、敵兵の本城に帰る道に当れば、何れに走るべきかと、只茫然として思案に暮れて居られけり。
(羽衣石南條記巻下 二十三―二十五頁 大正四年十月発行「因幡叢書」)
山名氏豊絶命 ならびに鳴瀧八幡由来の事
さても山名氏豊は宮内山を立出でて、因州の方へと心さし、小林源蔵と只二人、心細くも落人の身となりて、山路を東に指して急かれけり。さっと吹き来る山颪にも、追手の来るかと胸打ち噪がせ、日も呉竹の夜に紛れ、ようよう逃れて北方山、つづら折りなる細道を、覚束なくもたどりつつ、落行く先はいなば山、また返りこん身の程っも、神ならぬ身の白真弓。やがて山路を打越へて、田原の谷へ着き給ふ。此所へ源蔵が知人に、平助と云ふ農夫あり。されども戦国の習ひとして、人の心の許しかたく思ひければ、潜かに家の裏の方へ廻りて、先つ主君をば茗荷畑の片隅に忍ばせ置き、其の身は家の扉に立ち添ひて、暫く内の様子を伺ひけり。折しも平助が声として女房に申しけるは、今日橋津表の合戦に、羽衣石倉吉の殿原打負け給ひしとの風聞あり。落人の無きにも限られず。時に取っての饗応せんと思ふ。粥の余分や有るといへば、女房はわれも左様に思ひし故、最前より其の用意しつるなりと物語るを、源蔵之を立聞きて、さては夫婦の心掛け子細なしと、扉をほとほとと叩きければ、内より誰なるぞといふ。小林源蔵也、はやくはやくと呼びければ、平助聞きて、それはそれは痛はしやとて、早速出でて扉をひらき、事の子細を聞き氏豊を迎へて内に入れ、奥の一間に忍ばせ、ねんごろにぞもてなしけえる。誠に魚の淵に逃れ、窮鳥の叢に入りし心地にて、一日一夜休息し、明れば八月十五日、鹿野の方へと心さし、未明の比立出給へば、平助は見送り出でて行手を教へ、やがて暇を告げて帰りける。さて主従の人々は、月も入さの山かげに、そなたこなたと踏みまよひ、林の陰に立忍ひて、明るを待ちて居給ひけり。然るに處ろに、壁に耳ある譬に洩れず、八葉寺と云ふ所に、長田肥前とて強盗の張本ありけるが、疾くより之を聞き付て、是れこそよきもふけ也と、手下の者共を相かたらひ、倉吉の城主の首を討取て、吉川殿へ持参しなば、多分賞禄を賜はるべしと、三十余人を催ふして、跡を追かけて来る。程なく追付き、それなるは落人ならん逃すまじと呼はりければ、源蔵是を聞より真先にかけて進み来る長田が婿なる者を、抜打ちにして切倒し、主君を守護し、大勢を相手になして戦ひけるが、氏豊も源蔵と共に右左りと開き合せて、六七人まで切倒す。敵は猶も前後左右より切てかかる。此の時主従の人々は、前日の合戦に手疵数ヶ所負ひ、其上に疲れの癒へざる事なれば、其身金石にあれざれば、盗賊ども乱撃の下に、主従遂に討死して片野の露と消給ふ。痛はしかりける事共なり。さてもその後此の人達の怨霊、郷中の人々に祟りをなしける故に、郷人等之を神としてあがめ祭りて、今の世まで鳴瀧村の新八幡とて、武運長久を禱るは此氏豊の神霊なり。
(羽衣石南條記巻下 二十五―二十七頁 大正四年十月発行「因幡叢書」)